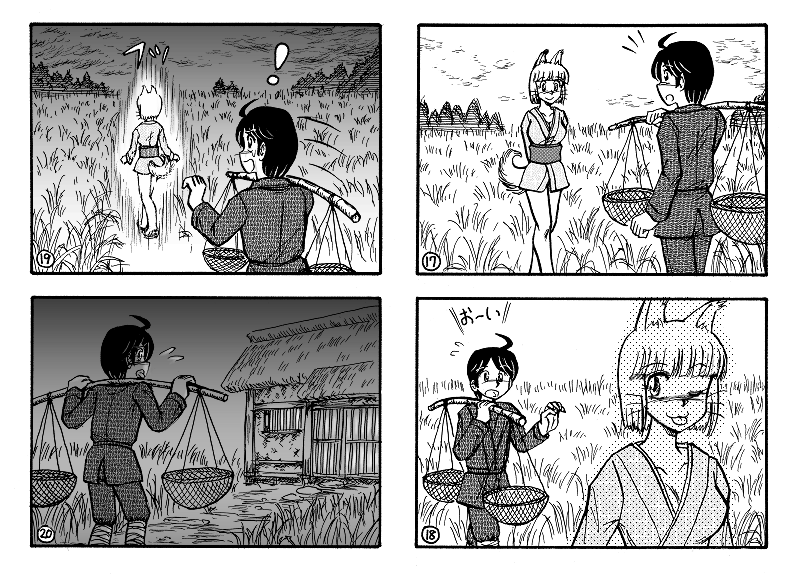
数日後、いつものように青年が木下まで仕入れに行った帰り道、宗甫の集落をすぎた辺りで、ふと前を見て驚いた。
道のまんなかにカメがポツンと立って、彼を待ち受けていたからだ。
「あれ、こんなところでどうしたの?」
「いつもお菓子をいただいてるお礼に、そうふけっぱらを抜ける近道を教えてあげようと思って」
そういうと、カメはスタスタと歩きだした。
青年は不思議に思いながらも、彼女の後に従った。
名前はカメでもさすがにいぬだからか、彼女の足の速いことといったら。
青年は荷物を担ぎ、息を切らしながら走ったが、ついていくのがせいいっぱいだ。
近道といったのに、辺りはどんどん見たこともない景色になっていく。
しかも、日がだんだん傾いてきた。
青年が不安に駆られていると、突然かき消すようにカメの姿が見えなくなってしまった。
途方に暮れる青年の目に、一軒の人家の灯りが見えた。
彼は仕方なく、疲れた体に鞭打って、その家を目指すことにした。


