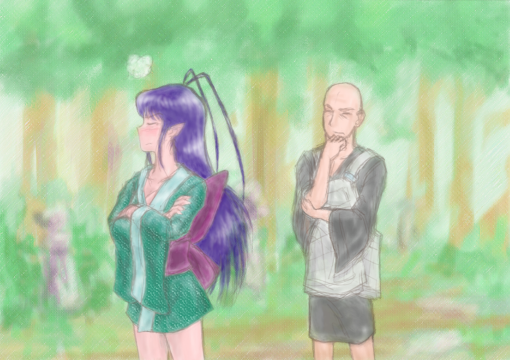
若い青年の僧がひとり、子らとたわむれる竜の姿を見つめていた。
僧の名は釈沖といい、まだ修行中の身であったが
女が本物の竜であることを見ぬくだけの眼力はそなえていた。
「その子らを贄にでもする気かね?」
釈沖が疑わしげに問いただすと、竜はつんとそっぽを向いた。
「フン、ニンゲンの肉なぞまずうて食う気がせぬわ。
沼の魚のほうがよっぽどましぞ」
「そうか・・・しかし、子守を引き受ける竜の話など聞いたことがないな。
といっても、お主はまだせいぜい蟠か蛟というところか。
沼の魚だけでは、高位の天龍になるまであと何百年かかるかしれんぞ?」
「たわけめ! 青二才の小坊主が知ったふうな口をきくな。
わしがお主の何倍生きてきたと思うとるのじゃ!」
竜が怒っていいかえすのを見て、釈沖は安心したようにうなずいた。
「まあ、天に昇るのをあせることもあるまい。
好きなだけ沼にいてくれ。村の者たちもよろこぶだろう」


